- Home
- ひらやま徒然日記
- わかりやすい税金のおはなし
- 仮想通貨の確定申告3
ブログ
12.242017
仮想通貨の確定申告3
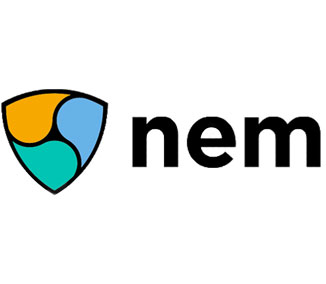
仮想通貨の所得の分類
さて、前回以前の記事では、まだ書いていなかったのですが、 仮想通貨の所得区分は、「雑所得」となります。 確定申告をされている方だとお分かりだと思いますが、 所得税の計算では、所得を10種類に分類して計算を行います。 例えば、商売をされている方では、「事業所得」、サラリーマンであれば、「給与所得」など、 基本的にそれぞれで計算方法が異なるため、その点ややこしいです。 仮想通貨は、その10種類の所得のうち、「事業所得」又は「雑所得」に分類して計算を行います。 中でも、「雑所得」は、他の所得と合算して計算を行う方式(総合課税) と、他の所得とは合算して計算を行わない方式(分離課税)があり、税金の計算は複雑になっています。 「事業所得」に該当するか「雑所得」に該当するかは、極端に言えば、 仮想通貨でご飯を食べていれば、「事業所得」。それ以外(サラリーマンの副収入的なもの)は「雑所得」になります。 本題の仮想通貨の税金計算は、先に述べた他の所得と合算して計算を行う方式(総合課税) で計算を行います。 サラリーマンでは、年末調整された給料にさらに仮想通貨による儲けが加算されて 税金の計算が行われるため、確定申告が必要になる場合(儲けが20万円超 ⇒ 仮想通貨の確定申告2)があります。 さらに、仮想通貨の税金計算が厳しいと言われている所以は、「損」をしたときの救済がなく、他のプラスの所得との 相殺ができません。 専門用語では、損益通算といいます。 これは、私の考えですが、仮想通貨取引が爆発的に進んで、法整備が追い付かなかった ことは、以前のブログ(仮想通貨の確定申告1)でも述べたところですが、 少し難しい話になりますと、分離課税にするには、申告分離課税にするか、 株式のように源泉分離課税にするかがありますし、いずれかになっても 他の所得との通算をどうするかなどの課題もあります。 なので、とりあえず総合課税にしといて、ということになったのではないかと思います。 もっとも、国税当局は、分離課税の要件を三種類(先物取引など)掲げており、 いずれにも該当しないので、総合課税とする見解を出していますが、 私は、将来的には、かつての外国為替証拠金取引(FX)のように、雑所得の分離課税に なるのではないかと考えています。仮想通貨での商品の購入
| 10万円の電化製品を購入するのに、0.2ビットコインを支払って決済しました。 なお、ビットコインは、以前に4ビットコインを195万円で購入しています。 |














